5感育安心食実践コース1期生スタート
5名の参加者で始まった、2月からの5感育食育実践資格取得コース。
座学を終了後、毎回の調理実習が始まっています。
全8回あるうち3回終了しました。
毎回写真撮る余裕がなくて(・・;)
定員5名です。
調理実習の準備が思っていたより、大変です。
前の日に食材の準備の買い出しに、ドレッシングや冷蔵スイーツなどは、前日に作ります。
私の手間はかかりますが、とてもやりがいがあって楽しいです。
4月~5月末までは、アロマ・アドバイザーコースの受講生が入校したので、次回の安心食実践コースは6月スタートとなります(*^^*)

そしてそして❤
なんと、宜野湾市認可園のここわ保育園、ゆうわ保育園さん(姉妹園)が、5感育安心食実践コースを本日よりスタートいたしました❣
保育園がですよ❣
毎週土曜日に、園に出向き保育士さんに講義をします。
9時半~15時✕2回。
そして週1で園の調理室にて調理実習。
園長先生の決断に感謝です。
本日から始まり、最後の調理実習は6月上旬終了予定です。
5感育安心食実践コースだけでなく、5感育タッチケア(愛着形成)の保育士向けへの9時間かけた講義もすでにスケジューリング。
「子ども達へ愛しているを伝えよう」
5感育タッチケアとは「あなたのことを大切に思っているのよ」を伝える手段の一つです。
ここわ保育園さんありがとうございますm(_ _)m
(園長先生の許可を得て、園の名前を出させていただいています)
安心食実践コースは、私が中学生の頃薬アレルギーを患い、体調がわるくなってもお薬を飲めない自分の体の健康を維持するために、20年以上食について学んで、こだわりにこだわり抜き、実践してきた調味料の作り方、調味料の選び方をお伝えします。
お薬を飲めない私にとって、「食」とは命を繋ぐものなのです。(湿布も使えなく、一部の麻酔も使用できません)
どなたにとっても本来の食は、命を繋ぐものなのですが、私にとって体調不良=死かもしれないのです。
そんな私は、ただ健康に良いから食育を実践しているのではなく、生きるために実践しているのです。
(アロマも同じです)
自己満足でもなんでもありません。生きるためなのです。
私の師匠に言われました。
「出来上がった調味料を使用してお料理を教えても、それは偽りの味だ。
今まであなたが実践していることを、生徒さんに伝えなさい。本物は必ず生き残る。」
魔法の粉を使わないお料理を学んでみませんか?

飲む点滴と言われる発酵食品「玄米甘酒」をふんだんに使用したお料理やスイーツ。
(たまに聞かれますが、甘酒とはお酒ではありません。発酵食品です😃)
お料理メニュー一部抜粋⇓
・粉なし油なしホワイトシチュー
・砂糖なし油なし油味噌
・ライスピザ
・3度美味しいミートソース
・油少ないマヨネーズ
・タルタルソース
・フワフワハンバーグ
・お肉で作る洋風だしの素
・美味しい味噌汁
・粉なし油なしクッキー
・オメガ3ココアから作るチョコレート
・ドレッシング各種(もずくドレ、人参玉葱ドレ、甘酒ごまドレなどなど・・・・)
・ソース各種
・万能調味料
・どこにもないティラミス
・フルーツそのまま発酵ジャム
・かき氷用発酵フルーツソース
・ソイアイスクリーム
その他・・・
安心食実践コースとしての資格取得は、家庭に活かすだけではなく、料理研究家として又は座学の講師として活かしていただけます。
今まで月に1度のペースで開催していたクッキングスクールを連続コースにしました。
なぜ、連続コースの資格取得にしたのかというと、1回や2回ではどうしても大切なことが伝わらないということがわかったのです。
私の伝えたことが、違う形で遠くの方に伝わっていたり、時間の制限で大切なことが伝えられなかったり、忘れていたり・・・
色んな想いを食を通して、しっかり伝えていきたい。
そう思ったのです。
今後は5感育安心食実践コースの90分講座として募集していきますね(試食付き)2,500円
または、一品クッキング4,900円

株式会社 NIPPON5感育協会代表
TOCCO
幼児期からの『5感タッチケア』オーガニック・無添加の食卓を作る『食育講座』などのプログラムを通して、五感を育みながら、子どもの好奇心、感性、知能を育てるメソッドを確立とし、2013年より活動をしはじめ、2016年に『NIPPON5感育協会』を設立。
子どもの心は、スキンシップも食も大人の手で育んでいくことの大切さを伝えることを、心手育(COTECCU)として子どもを生んだら子どもに寄り添って育てる大切さを伝えている。
3人の娘を育てる母として、子育ての中での「発見」や「気づき」を「NIPPON5感育協会」のコンテンツとして、忙しい子育てママに提供する活動を続けている。














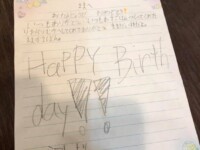
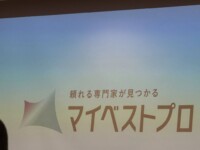


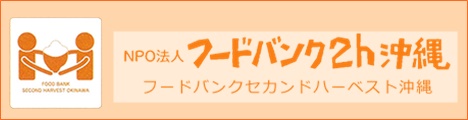





この記事へのコメントはありません。